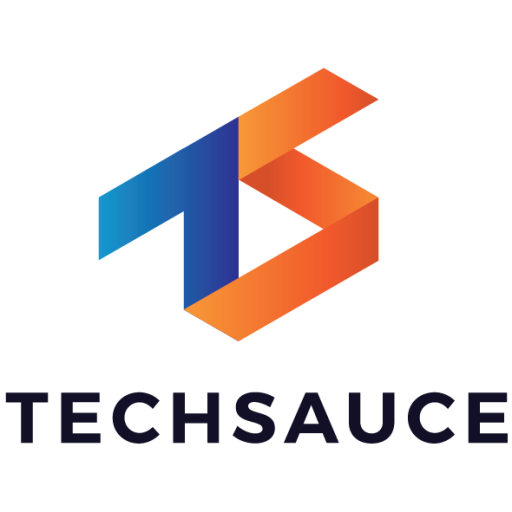SNS上のアクティビティで共通の趣味同士をつなぐ新しいマッチングサービス Dipify.com
Dipifyは共通の趣味をもつ相手をSNSのアクティビティによって見つけ出す新しいカタチのマッチメイキングサービスだ。独自のアルゴリズムとデータを使用することで短時間で最適な相手とのマッチングが可能。
ー簡単な自己紹介とDipifyを始めるに至った経緯を教えて下さい。
SNSを使ったマッチングアプリケーションDipifyの創業者Natawonと申します。生まれはタイで育ちはカナダです。大学では観光学とホテルマネジメントを学んでいました。Dipifyを 始める前はカナダで婚活イベントの企画、運営を行う会社で働いていました。担当していた職種内容は、主にイベントの企画やクライアントリサーチでした。参 加者が短時間で共通の趣味嗜好をもった相手を見つけ出し、短絡的ではない持続的な関係へと促すためのシステムなどを考案し実施していました。
ーDipifyについて教えて下さい。
Dipifyは人をマッチングさせるモバイルアプリケーションとウェブサイトです。サービスの最大の特徴は、リアルタイムでSNSと連動している点です。具体的にFacebookのシェアやYOUTUBEのコンテンツ視聴といったSNS上のアクティビティと連携して、あるユーザー同士が同じタイミングで同じ動画や記事のシェアなどをした際に、アプリケーションから通知が行く仕組みとなっています。従来のマッチングサービスと違い“セレンディピティ”のような偶発性のある出会いにフォーカスをしています。そうすることで、チャットや実際に会って話したときの会話の内容がより有意義なものとなり、短い時間でより効率的に相性の良い相手とマッチングができます。
ーサービスを始めるきっかけとなったのは何ですか?
わたしたちがDipifyを始めたのは、マッチングサービスの需要はあるにも関わらず、既存のサービスがあまりにもクライアントの要望に応えられていないと感じたからです。例えば、これらのサービスを1年利用した場合、会員費用として高いものだと約5000ドル支払います。つまり、決して安いとは言えないこの金額を支払っても、自分と相性の良い相手を探そうとしている人は一定数存在するということになります。
わたしたちは、この一定数のクライアントが求める価値に目をつけました。そして、彼らのためにより簡単に短時間で自分の趣味趣向に沿った相手を見つけてもらう方法を考え、現在のSNSを通してお互いの好みを簡単に知ることの出来る方法を見つけました。
ーマネタイズはどのように行っていますか?
フリーミアムモデルを採用しています。基本的な機能は無料で、アプリ内の付属コンテンツ機能は有料で提供します。たとえば、マッチングする相手の条件にフィルターをかけたり、チャットに使用するステッカーの購入などです。これらは一度購入するとモバイルでもウェブでも両方使用することが可能です。ユーザーがこれらの機能を導入することで、わたしたちは各ユーザーのパーソナライズ化が可能となり、マッチングさせる相手の精度をあげることが可能です。
有料コンテンツの料金は1.99ドルから9.99ドルとなっています。また、フリーユーザーは、デジタル広告が自動的に表示される仕様となっていますが、これはもうひとつの収益構造となっており、ターゲティング広告などを活用した広告収入を考えています。今後、わたしたちのサービスがよりアクティブユーザーの数を獲得することができたら、競合サイト向けにアフィリエイト広告掲載を展開していきたいと考えています。
ー東南アジアにはすでに多くのマッチメイキングアプリケーションが存在していますが、それについてはどう考えていますか?
マッチメイキングやデートサービスの市場は飽和状態であると感じます。ユーザーにとってはまさに選び放題で、実際に、彼らがこういったサービスを利用する際は複数のサービスを同時に試します。彼らは出来る限り多くのサービスを利用することでより相性の良い相手と出会う可能性を高めたいからです。
しかし、そういった行動傾向と従来の大量紹介型のマッチメイキングサービスが合わさってしまうとデメリットが生まれます。ユーザーは毎日膨大な人数の相手を紹介されても、ひとりひとりとの深いコミュニケーションが取れないという事が起きてしまうのです。相手が自分と相性が良いかを確認できないまま時間と労力を費やしてしまいます。
ーDipifyが他のマッチメイキングサービスと異なる点は何ですか?
短時間で適切な人物を紹介できるところです。そして彼らに対して、自然で円滑な、すぐに打ち解けられるような会話のエッセンスを提供できます。それは、先程からお伝えしている、SNS上での共通アクティビティです。
ユーザーは自分のSNSアカウントをアプリに連携するだけで、それ以外に特に何もする必要はありません。SNS上で自分と同じタイミングで同じことをしている場合のみDipifyから通知をするので、そのときに改めてアプリケーションを起動して、会話を始めればいいのです。たとえば、YOUTUBEで同じコンテンツを視聴していたり、Facebookで同じ場所にチェックインしたとき、また同じコンテンツをシェアしたり、といった時が対象となります。
https://youtu.be/l0fCKhMNYho
Dipifyは人間の感情をベースにした正真正銘の双方向型マッチングサービスです。わたしたちは今までに存在しなかったような新しいコミュニケーションのカタチを提供していきたいと考えています。
ー東南アジアのマッチンメイキングサービスに関するトレンドと成功しているサービスの特徴についてはどのように見解をお持ちですか?
マッチメイキングやデートサービスのユーザーの特徴として、彼らは自分たちが引っかかるような出会いを見つけるまで複数のサービスを試す傾向にあると考えています。また、東南アジアの特徴としては、特にシンガポール、インドネシア、マレーシア、ベトナム、フィリピン、タイランドはマッチメイキングサービスを使用することにあまり抵抗が無いと感じます。タイの次に大きな市場となるのは、人口が他の周辺諸国と比較してとても多いインドネシアだと考えています。
ースタートアップで一番苦労することは何ですか?また、それはどのように解決できると思いますか?
共同創業者を見つけることですね。また、彼らをマネジメントして事業の基板を創り上げていくことも難しいです。スタートアップの人々はあまりこのことを話しませんが、同じ目的をもったメンバーを見つけることと今後の予測を行うことはスタートアップにおける最も大きい挑戦であると思います。
しかしながら、わたし自身は現時点までとても物事がうまくいっているので、こういった問題に直面したことはありません。しかし、常に誠実で真剣であることはスタートアップを円滑に運営するために必要不可欠であると思います。
ースタートアップで目指している存在はいますか?
Mark・Cubanですね。彼はスタートアップにおけるやり手で、起業家たちの間では、最も有名な実業家として有名です。驚いたことに、彼は12歳のときから自身でビジネスをはじめていて現在は億万長者です。
ータイと東南アジアにおける次のターゲットと投資に関してはどのように考えていますか?
まず、タイでダウンロード数を増やし、サービスの認知度を上げます。そしてユーザーからフィードバックを集めて、サービスの改良をしていきます。今後の展開は、インドネシア、台湾にサービスを広めていきたいと考えています。もちろん、その為に一緒に戦略を考えてくれる投資家を探しています。
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด