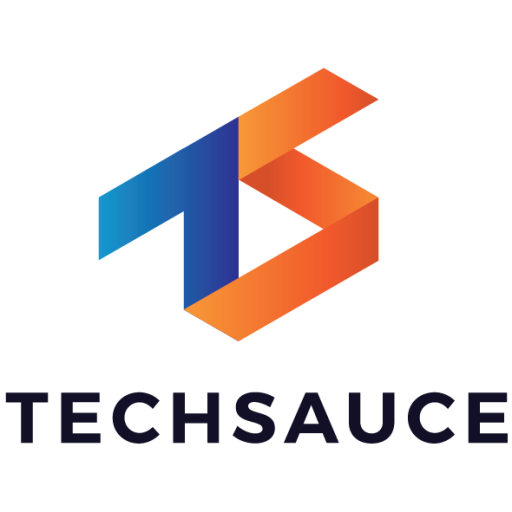【※追記あり】着信時に発信者を確認できる迷惑電話防止サービス「Whoscall」
Whoscallとは自分の知らない番号から電話があった時に、発信者の情報を自動的に特定し表示する事ができるサービスだ。迷惑電話などの防止策として役に立つ。
電話にでる前に発信者の確認ができるため、迷惑電話、テレフォンセールスによって自分の大切な時間を邪魔されない点が特長だ。さらに、宅急便会社などその場ですぐに対応したい電話番号も表示されるのが嬉しい。アプリケーションはAndroid、iPhone、WindowsPhoneに対応しており、現在まで2000万ダウンロード、7億の電話番号のデータベースを保持している。台湾、香港、日本、ブラジル、そしてタイの5カ国を拠点に世界中でサービスを展開している。
タイの拠点は2014年の5月に置かれたそうだ。今回はタイ拠点、唯一のグローバルビジネスディベロッパーであるYuting Liu氏にサービスとタイのマーケットの特徴について尋ねてみた。
ーWhoscallについて教えてください。
Whoscallと はGogolook株式会社が運営する、電話発信者の身元を特定して通知するアプリケーションです。アドレス帳に登録がない番号から電話がかかってきた際 に、発信者の情報を画面上に表示させることが出来ます。そうすることでクレジットカード会社や銀行からのセールス電話やスパム電話などの着信によって、会 議や仕事を中断させられることが無くなります。
ー電話番号のデータはどのように収集しているのでしょうか?
現在、保持している電話番号のデータ数はおよそ7億です。データの収集方法に関しては、利用ユーザーに発信者のタグ付けをしてもらったり、また企業や店舗などが電話番号を載せているイエローページ(タウンページ)から収集しています。主にローカルコミュニティによるタグ付を情報源にしています。また、独自のデータサーバーも使用してスパム電話の特定も行っています。例えば、1分につき5秒のペースで様々な番号に通話をかけている不審な番号はテレフォンセールスかスパム電話だと認識され、サービス利用者にその様に表示されます。
ー世界中で展開されているサービスですが、サービスが初めてリリースされたのはどの国ですか?
Whoscallは2012年に台湾で初めてリリースされました。3人の台湾出身の共同創業者たちが運営していていたのですが、当初は3人とも本業があり、その片手間として立ち上げたサービスでした。天気となったのは、ある時にGoogle元CEOエリック・シュミットが台湾でスタートアップに関するピッチを行った時でした。その際に「台湾はイノベーションを起こすのにとても最適な場所だ。その象徴となるのがWhoscallである。」と紹介したことで一躍有名になりました。その時はまだ多くの人に知られたサービスではなかったので、その場でにいた人たちは全員はてなマークが浮かんでいたようですが。笑
ー東南アジアから南米までと、世界中に幅広く拠点を置かれていると思うのですが、どういった基準で選んでいるのでしょうか?
まず、これらの国の共通した特徴として、他国と比較して特にWhoscallの使用割合が高い国であること、人々がどの様な目的で電話をするのかといった動機がとても似ている、という点が挙げられます。つまり、非常にマーケティングがしやすく、参入障壁が低いのです。例えば、タイはスパム電話やテレフォンマーケティングによる電話発信が近年増加傾向にありますが、実はこれと似た現象が約2年前の台湾で起きていました。スパム電話に関しては台湾では減少傾向にありますが、それはスパム電話を行っていた組織が場所を南下して、タイで活動しているという理由があります。他の国に関しても同じで、一見すると共通点がない様に見えますが、こういったスパム電話やテレフォンマーケティングが多い点が共通しています。そういった国に対しよりサービスをローカライズさせる為に海外に複数拠点を置いています。
 Whoscall - Global Business Development - Yuting Liu氏
Whoscall - Global Business Development - Yuting Liu氏ーYutingさんはどの様な経緯でWhoscallに入社したのでしょうか?
私は生まれと育ちはタイなのですが、大学は国立台湾大学でコンピュータエンジニアリングを学び、ノートパソコンに使用するマイクロチップの開発などをしていました。その後、インターンとして台湾のTMIというベンチャーキャピタルで投資アナリストとして働いていたのですが、その際にたくさんの起業家と出会い、彼らの面白いビジネスを間近で見ていてとても刺激を受けました。その経験があって、自分でもビジネスを始めようと思い、農家を対象としたビジネスコンサルティング、マーケティング、販売プラットフォームの作成などを行い、1年ほど運営しました。その後、知人の紹介でGogolook社に入社して現在に至ります。昔から「あらゆることに楽しみながら挑戦する」ということを自分の行動基盤にしているのですが、Whoscallのタイ立ち上げ事業は非常におもしろいと感じます。タイと単にいっても、タイ全体とバンコクではモバイル端末市場の内訳は大きく変わりますし、マーケティングの手法も全く異なるので日々いろいろなことを試して、新しい気づきを得ています。
ータイでWhoscallをよりローカライズさせるためにはポイントとなる点は何ですか?
タイを拠点にした本格的な活動は2014年の5月からで、現在はユーザーヒアリングをしてタイの市場調査をしている段階です。先ほどもお伝えしたように、タイと台湾の通話目的は非常に似ています。例えば、テキストでのやり取りよりも電話を使ったやり取りを好む点などがそうですね。ですが、ミクロレベルでみるとやはり様々な違いや人々の好みがあります。なのでまずはそういった部分を的確に把握することが最優先ですね。そして次の段階が、マーケティングキャンペーンなどを通してサービスの認知度をあげること、またはタイのローカルサービスと連携をしていくことを考えています。そしてある程度、タイにおけるサービスの認知度や市場の特徴が掴めたらその情報を生かして、また次のビジネス市場へとサービスを拡大していくと思いますね。
ー最近の傾向だと、LINEやKakaoTalkといった無料通話・メッセンジャーアプリケーションが使われ、固有番号を使用する光景が少なくなっていますがそれについてどう考えていますか?
確かに、最近は無料通話や簡易メッセンジャーサービスが友人同士の会話だけでなく社内でのやり取りでも頻繁に使われています。しかし、電気、水道、ガスなどの公共事業に関する問い合わせや、ビジネスにおけるクライアントのやり取りとなると、やはり固有番号を用いた通話の方が需要があります。また、もし仮にこれらの無料通話・メッセンジャーアプリケーションがあらゆるシーンで頻繁に使われるようになったとしても、弊社のサービスの内容はあくまでも発信者の通知による受信者の安全性の確保という点に基盤を置いていますので、そういった会社にサービスを提供することで対応していけると考えています。
【※追記 2015年4月8日】
「現在まで2億ダウンロード、70億の電話番号のデータベースを保持している。」
↓
「現在まで2000万ダウンロード、7億の電話番号のデータベースを保持している。」
の誤りでした。修正いたしました。
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด